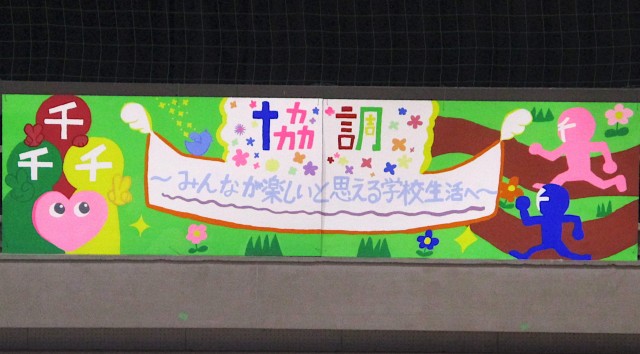来訪者の方へ
小田原市立千代中学校のホームページへようこそ!
「積極的に挑戦し一生懸命な人」「人の心を考えて行動できる人」 「地道な努力ができる人」 それが千代中ヒーロー
千代中学校 学校教育目標 「自律 協力 挑戦」
新着記事
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7月13日(日)県西ブロック中学校総合体育大会
- 公開日
- 2025/07/13
- 更新日
- 2025/07/13
できごと
いよいよ県西ブロック大会の開幕です。小田原アリーナでは、男女バドミントン団体の部...
-
-
-
-
-
-
-
-
-
新着配布文書
-
R7 3学年学びプラン PDF
- 公開日
- 2025/07/07
- 更新日
- 2025/07/07
-
R7 2学年学びプラン PDF
- 公開日
- 2025/07/07
- 更新日
- 2025/07/07
-
R7 1学年学びプラン PDF
- 公開日
- 2025/07/07
- 更新日
- 2025/07/07
-
- 公開日
- 2025/07/04
- 更新日
- 2025/07/04
-
- 公開日
- 2025/06/03
- 更新日
- 2025/06/03